 |
|
|
現在の秋田県大館比内地方は大昔は陸奥国の一部と認識されていたようです。 |
|
| 鎌倉から南北朝 | |
| 河田次郎後の比内地方は壇ノ浦の合戦で活躍した弓の豪者甲斐源氏、浅利与一義成(義遠)が比内郡一円を所領する地頭となったとされている。ただ比内郡へは直ちに赴任せず、代官を派遣したのではないかと考えられている。 | |
|
|
|
 |
|
|
現在の秋田県大館比内地方は大昔は陸奥国の一部と認識されていたようです。 |
|
| 鎌倉から南北朝 | |
| 河田次郎後の比内地方は壇ノ浦の合戦で活躍した弓の豪者甲斐源氏、浅利与一義成(義遠)が比内郡一円を所領する地頭となったとされている。ただ比内郡へは直ちに赴任せず、代官を派遣したのではないかと考えられている。 | |
|
|
|
| 同時期、奥州に入った南部氏も数代は代官赴任で、鎌倉に本拠を構え墓所も鎌倉に置いたことからも当時の風潮が推測できる。南北朝時代になって、比内郡も同様に混乱の時代を迎えるが、そこでは浅利六郎四郎清連という強い武将が活躍する。ただ浅利与一系との系脈は不確実だが、時代背景からして連綿的同族と考えていいだろう。 | 地頭入領 |
| 戦国争乱 |
| 数代の後、浅利兵部大輔則頼の時代は比内郡の安定期であり、かつ勢力領土拡大期で、天文19年頃は鹿角地方を含めた米代川流域の北鹿地域をほとんど制覇した。支城と領土の確立期でもあり、則頼は平穏のうちに他界した。 |  |
|
|
|
| 群雄割拠 | その後嫡子、浅利則祐が浅利宗家の頂点に立つが、永禄5年頃あえなく宿敵安東氏の軍門に下り長岡(扇田)で自害、その後を継いで弟の浅利勝頼が浅利家を引導、大館に進出築城する。ここでも天正10年家臣の裏切りで勝頼が討たれて浅利家の脆弱性をさらけ出す。 |
| 南部、安東、津軽氏との戦乱 |
 |
浅利氏の本拠地比内領は南部領、津軽領、檜山領と隣接する地理的環境から、しばしばその領土を巡り戦乱となる。則頼までは平安だったが、則祐以来、この比内の地が戦場となり人心の荒廃をもたらし、その不満が内部からの崩壊となっていった。 |
|
|
|
| 文禄頃になって、檜山安東氏との確執がこじれ、天正10年以来、屈辱の配下として従属していた鬱憤が爆発、物成(租税)問題で浅利頼平は檜山と合戦に至り、秀吉からの矢留(停戦)令を受ける。この頃中央では秀吉の後継問題で勢力が二分されつつあって、その派閥が浅利安東問題へ影響を与える。 | わかりやすい 浅利史 |
| 天下評定 |
| 比内崩壊 | 秋田安東氏との紛争裁定は大坂表に計上され、頼平自身が上方へ登る強い決意を示した。しかしその大坂滞在中に頼平は急死してしまうのである。一般には奥州から大坂へ上るには相当の覚悟と体力を必要とする。病弱の身であればともかく頼平は健康であったと思われる。そこが謀殺説で語られる所以なのである。 |
|
|
|
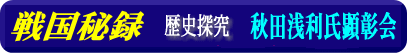 |